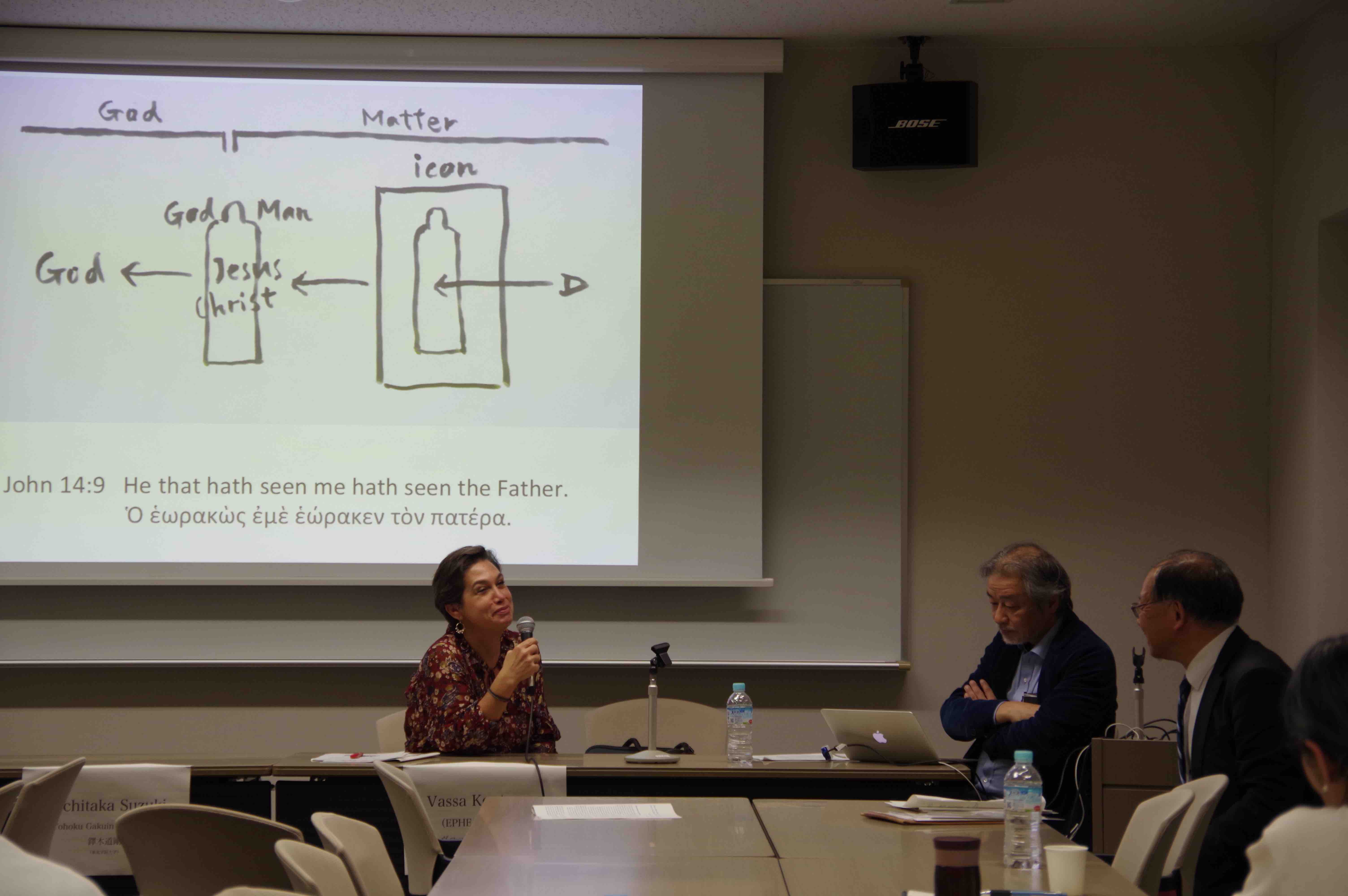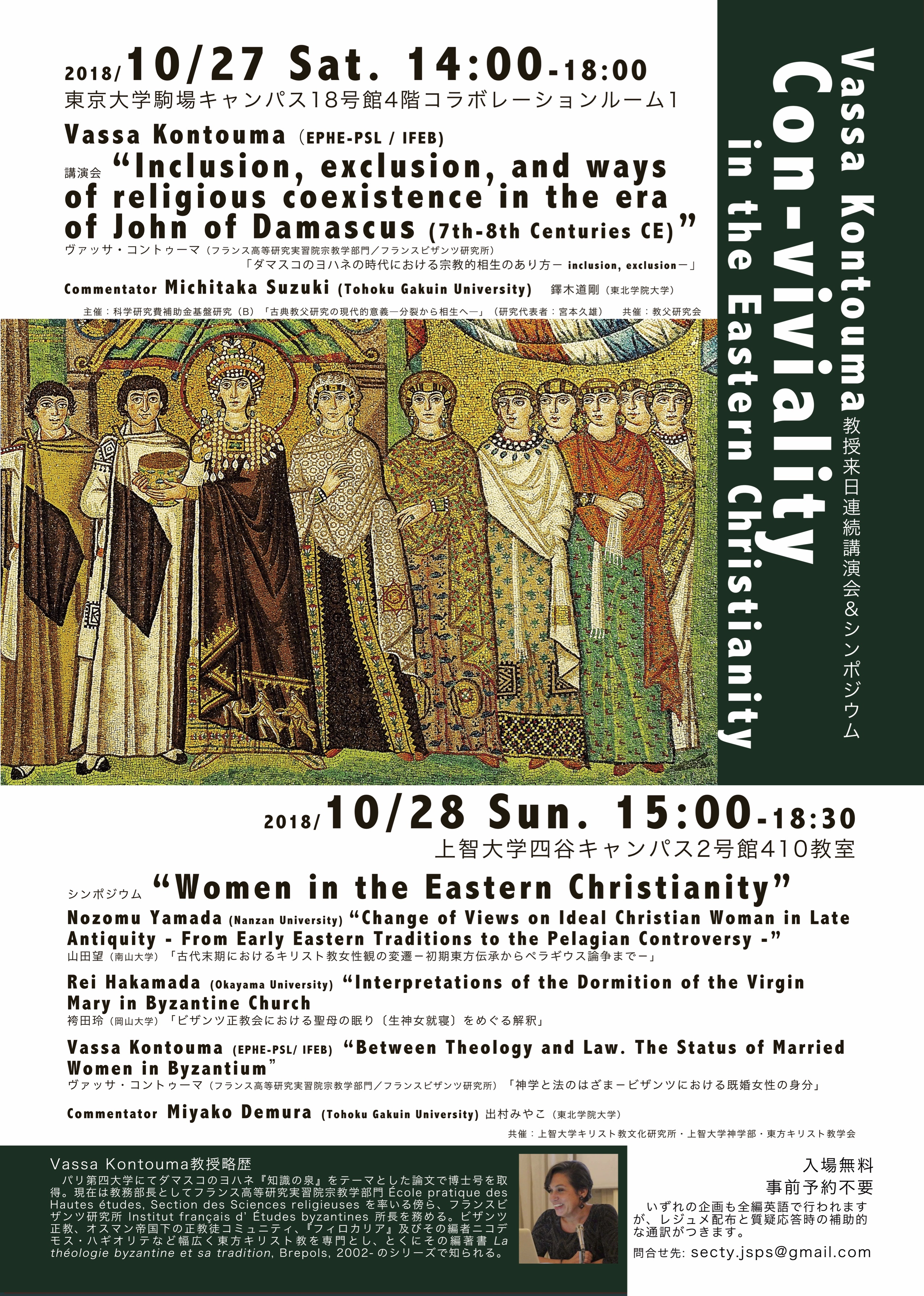直前のご連絡となり大変恐縮ですが、3月28日に予定していた第171回教父研究会例会について、延期することにいたしました。
今後の予定については、再度調整のうえ改めてご案内をいたします。
====================
第171回教父研究会は、2020年 3月28日(土)14時から18時まで、東京大学駒場キャンパス10号館3階301号室において開かれます。通例の会場と異なりますのでご注意ください。
発表題目 1:神学者の言葉の伝統―ナジアンゾスのグレゴリオスとビザンツの教養
発表者:発表者:窪信一(東京大学)
メッセージ:
ホ・テオロゴス(神学者)の称号で呼ばれるナジアンゾスのグレゴリオスの東方における権威と重要性については特に説明の必要はないだろう。しかし彼にその死後において人々の尊敬を集める媒体となった彼が書き残したもの、彼のギリシア語については、その果たした役割と伝統の歴史が詳らかになっているようには思われない。その著作がいかに深くビザンツのギリシア語を使うキリスト教徒の読書生活に根付いていたかは、浩瀚な写本の伝承はもとより、幾人もの手による注解、さらには古典作家への注釈や修辞学の教材や辞典や単語帳の類に頻繁に表れる用例、そしてビザンツの知識人たちが自分たちの著述で時には名前を挙げて引用し、時には全く典拠を明示せず引喩する神学者の言葉が、示唆している。
グレゴリオスは、哲学と修辞学、異教の学問伝統の中心地であるアテナイに長期間の留学経験を持ち、その文業で教養あるキリスト教徒の在り方を体現し、後世のビザンツ人にとってその理想の模範であり続けた。そして異教徒(ヘレネス)とキリスト教徒の学知の関係が問題となる時に彼の言葉がどのように働いたか、本報告では14世紀の神学論争におけるそのいくつかの事例を通して、古典と教父、二つの層からなるビザンツの教養の在り方に迫っていきたい
発表題目 2:停思快(delectatio morosa)について 現実と想像の関係について近現代の思想が教父文学に学んだこと
発表者:森元庸介(東京大学)
(発表要旨は追ってお送りします。)
この件に関するお問い合わせは下記教父研究会事務局にお願いいたします。
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻・高橋英海
E-mail: takahashi[at]ask.c.u-tokyo.ac.jp